防災用の備蓄品を収納するならトランクルームを活用すると良い3つの理由

※本記事にはプロモーションが含まれています。
災害大国の日本では、地震、台風、集中豪雨など、毎年様々な災害が襲ってきます。
それに加え、パンデミックやネットのデマですら多くの人の生活に影響を与える時代になり、どこに住んでいても危機が身近になっています。
そんな中、災害や緊急事態の備えに対する意識が高まったことで、防災グッズや災害時に役立つアウトドア用品が人気となっています。
しかし、「防災グッズや備蓄品などのかさばる荷物を収納するスペースがないので、思うように備蓄ができない」という悩みをお持ちではありませんか?
そんな方には、トランクルームがおすすめです!
なぜトランクルームが防災の備蓄品を収納するのに良いのか、その理由を3つご紹介し、上手に使いこなすヒントもご説明します。
目次
理由① 防災用の備蓄を家で収納するにはスペースが足りない

まず、防災の備蓄は何日分用意すると良いのでしょうか?
一般的に、大型災害が起きた場合、発生後3日間は人命救助を最優先するため、ライフラインや物流の回復スピードは遅いです。
そのため、防災ガイドでは飲料水や食料、常備薬などを最低3日分、可能なら1週間~10日分を備蓄するよう勧めています。
では、ライフラインを含めた3日分の備蓄はどれくらいの量になるのでしょうか。
さらに、大規模災害でライフラインはどのくらいの期間で復旧し、それに合わせてどれくらいの量を備蓄したらいいでしょうか。
電気の復旧にかかる日数

まず、電気が復旧するまでの目安は4日で、ライフラインの中でも短期間で復旧します。
3日分であればモバイルバッテリーや乾電池、少容量のポーダブル電源といった手軽な電源で必要最低限をカバーすることができるので、収納スペースは確保しやすいでしょう。
しかし、復旧したとしても供給が制限されたり、断続的な停電の可能性もあるので、大規模な災害にも備えるなら1週間以上の備蓄が望ましいでしょう。
災害時に電気を使用するシーンとして、通信機器の充電や照明といった消費量が少ないものや、調理や暖冷房機器といった消費量が多い機器が想定されます。
これらを不自由なく使用するには1人1日約1~2kWhが必要とされています。
3日目以上に備えつつ消費量が多い機器なども頻繁に使うなら、ポーダブル電源やインバーター発電機で対応できます。
とはいえ、キロワット(kWh)単位のバッテリーが付くと機器のサイズが大きくなりますし、ソーラーパネルなども合わせると広いスペースが必要になり、一気に収納のハードルが高くなります。
水道の復旧にかかる日数
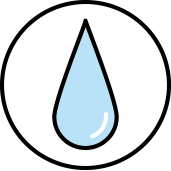
次に、水道が復旧するまでの目安は約1ヶ月です。
水道の復旧は、破損部分を特定し、掘り起こして交換する、という大変な作業になります。
さらに、避難所や病院などの施設を優先的に復旧させるため、どうしても時間がかかります。
そのため、3日分では全く足りませんし、避難生活が長引くにつれて洗濯や行水、トイレなど生活用水の量も日に日に増えますので、1週間以上の備蓄が良いでしょう。
備蓄の量は、1人1日3ℓが目安となるので、3日分なら9ℓ(500mlのペットボトル18本)、1週分なら21ℓ(500mlのペットボトル42本)、復旧までの30日分なら90ℓ(500mlのペットボトル180本)が必要です。
とはいえ、これは飲料分だけの計算なので、洗濯、洗浄、調理、ボディケアなどの生活用水も含めると倍以上必要になります。
水の場合、災害後3-4日頃から行政が給水所や給水車で提供を始めるので補給できますが、人数が多くて供給が追い付かないケースが多く、補給できるのは数日ごとになる可能性もあります。
それで、1度にできるだけ多く確保するには頑丈で大きなウォータータンクが必要ですが、普段の生活の中で大きな空のタンクを収納しておかないといけません。
ガスの復旧にかかる日数

最後に、ガスが復旧するまでの目安は約1-2ヶ月です。
ガスは水道とは違い火災や爆発の危険があり、手順が多く個別の点検も必要になるため復旧にはかなり時間がかかります。
そのため、大型の災害時には3日分以上の備蓄が望ましいでしょう。
ガスボンベは、カセットコンロでの調理、暖房器具、照明器具などに使用できますが、例えば、食事のためだけで使用する場合、1食分の調理で強火を約15分間、毎日3食使用した場合、250gのボンベ1本を1日半~2日で使い切る計算になります。
メーカーによるとボンベの燃費は季節に影響を受けやすく、冬の方が消費量が多いようですので、3日分は1人あたり3本パックを1セットあれば問題ないでしょう。
最近は電子調理器もあるのでガスより電気に頼ることもできますが、火が使えるメリットは大きいので、最低でも3日分は備蓄しておくと安心です。
もし、30日間3食分に使用するなら、3本パックを8セットも備蓄する必要があります。
最低3日分の備蓄に必要なスペース
では、備蓄品を保管するのにはどのくらいのスペースを埋めることになるでしょうか?
最低限必要な1人3日分の備蓄を収納するとおおよそ次のようなサイズになります。
【ポータブル電源】40 × 21.1 × 28.1cm (約1000Wh 1台)
【水】37 × 25 × 22.1cm (500ml×24本入り)
【ポリタンク】24 × 13 × 16cm (5ℓ 1台)
【カセットガス】20.4 × 7 × 20.0mm (3本セット)
この5つの備蓄品だけでも押し入れの1/8の面積を占領する計算になります。

2人分になると押し入れ1/4、4人分なら1/2になり、加えて衛生用品やペーパー類などの生活用品など合わせると3日分だけでもかなりの量になります。
ですから、必要最低限の3日分の備蓄を収納するだけでも収納スペースが圧迫されることになるでしょう。
集合住宅は収納スペースが戸建てほど広くないので、3日分だけでも精いっぱい、3日以上の量を全部収納することすら難しいかもしれません。
ある調査によると、約2万人のうち3日分の備蓄をしているのは40%程度、という結果になるのも納得できます。
そんな時こそ、トランクルームを活用して備蓄品を収納することで、家の貴重な収納スペースを無駄にすることなく、1週間~10日以上の備えが十分できます。
- トランクルームを活用すると、家の貴重な収納スペースを備蓄品で埋める必要がなくなる。
理由② 防災用の備蓄を家だけでストックすると失うリスクが高い

家だけで防災用の備蓄を保管すると、どのようなリスクがあるでしょうか。
まず、災害の影響で家が倒壊、浸水、火災の被害を受けて備蓄品を失ったり、家から取り出せない状況になる可能性があります。
また、2次災害や空き巣の被害も想定すると、防災用の備蓄を1ヵ所だけで保管するにはリスクが高いと言えます。
それで、いくつかの場所に防災用の備蓄を分散しておくなら、失うリスクを減らすことができます。
分散する先として、トランクルームはとても好条件です。
トランクルームは、荷物の収納スペースを貸すサービスで、一般的に頑丈で倒壊するリスクが少ない建物やコンテナを使用しているので、災害時に役立つセカンドスペースとしてピッタリです。
また、浸水のリスクにも対応するなら、室内型は2階以上、屋外型は2段目以上を選ぶとよいでしょう。
さらに、収納庫には頑丈なカギが付いており、万が一建物や敷地に侵入されても中の荷物に手を出すのは難しいため、盗難のリスクも少ない環境だと言えます。
しかも、もしトランクルームに入れた荷物に直接被害があった場合は、補償サービスが標準またはオプションで付く会社もあるので、事前に確認することをおススメします。
- トランクルームに備蓄品を収納するとリスク分散になる。
理由③ 災害後に安全な収納場所があると便利

トランクルームは、備蓄品や防災グッズの収納以外にも役立つシーンがあります。
例えば、自宅以外の避難生活になったら衣類の収納場所として使えますし、自宅の荷物の一時退避場所としても活用できます。
また、使い方は防災用の備蓄の収納だけに限らず、普段はあまり手に取ることのない思い出の品の置き場所とすれば、家に被害があっても大事に残すことができます。
防災グッズの倉庫としてセカンドスペースを確保しておけば、収納の用途として幅広く使うことができますので、災害後にとても役立ちます。
他にも気になる使い方があれば、「トランクルームでこれやってもいい?ちょっと気になる9つの使い方」もご覧ください。
- トランクルームを借りておくと、災害時にセカンドスペースとしていろいろな用途に使えるのでとても便利。

どのように防災用の備蓄品をトランクルームへ収納するといい?

トランクルームに備蓄品を収納するなら、何をどのように入れるとよいでしょうか。
3日間分の備蓄は避難時の持ち出し袋に入れたほうが良いので、主に分散の対象は4日分以降のための備蓄品にしましょう。
分散する分量を決めるには、自宅とトランクルームの立地での被害予想を考慮しましょう。
地域の防災マップや防災ガイドに載っている浸水や土砂崩れの被害予想や、交通規制でも行けるお店へのルートをチェックします。
自宅の方に被害が予想されるのであれば、トランクルームへ多めに収納するとよいかもしれません。
逆に、トランクルームに被害が予想されるなら重要度の低い荷物だけにとどめておくか、または頑丈なケースに入れて収納するといった方法がとれるでしょう。


トランクルームに防災用の備蓄をするうえで注意すべき点はある?

災害に備えてトランクルームに防災用の備蓄を収納するなら、復旧が遅れても長期間しのぐことができますが、あくまでリスク分散の手立てであり、頼りすぎて損失が大きくなることがないようにしてください。
災害後のムリな移動や荷物の運搬はリスクが伴いますので、運営会社に連絡を取ってお店の状態を確認し、明るい時間に余裕をもって動けるタイミングで出し入れしましょう。
保存がきかない食品や臭いが出る食品はトラブルの原因になりますので、未開封の保存食を入れるようにしてください。
また、保存食は高温多湿を避けた方が良いので、コンテナ型の屋外型ではなく室内型で空調が設置されたお店がオススメです。
ガソリンや石油などの燃料は引火の危険がありますので、収納することはできません。

このような点を注意して、トランクルームを活用した防災用の備蓄備蓄をおすすめします!
近くにいいトランクルームがなければ「宅配型トランクルーム」

必ずしも、お住まいの地域に頼れそうなトランクルームがないならどうしたらいいでしょうか。
そんなときは、「宅配型トランクルーム」という選択肢があります。
「宅配型トランクルーム」とは、荷物を入れたボックスを宅配業者に運んでもらい、専用の倉庫に預けることができるサービスです。
預けたボックスを取り出すには、利用しているサービスのウェブサイトから依頼して、宅配業者に届けてもらうことができます。
宅配型トランクルームは災害時にも使えるの?配達再開の目安は?
宅配業者または道路がどれだけ被害を受けているか次第になります。
では、災害後どれくらいの期間で宅配業者が回復するでしょうか。
2011年の東日本大震災では、大手3社は発生後12日程度で配達を再開しましたが、通常より2-10日程度かかったり、被害が深刻なエリアは営業所止めになるなど全面回復までにはかなり時間がかかっています。
2024年の能登半島地震では、全営業所の再開は発生後から約半月かかり、配達が通常より1ヶ月もかかるケースもあったようです。
それで、目安として早ければ発生後10日後頃から、再開後も届くまでに1ヶ月以上かかるケースもあると考えておくと良いかもしれません、
また、街の中心部や主要道路は、救助や救援のために復旧が早く進むので荷物が早く届く可能性が高く、災害時に役立つと言えます。
しかし、中心部から遠く離れたエリアでは、復旧に時間がかかり荷物が届くのにかなりの時間を要する可能性が高いかもしれません。
とはいえ、移動手段や燃料が限られた中で、わざわざ届けてくれるというのは、とても助けになるサービスではないでしょうか。
宅配型トランクルームを使う注意点は?
宅配型トランクルームを使う注意点がいくつかあります。
1つ目に、備蓄品を失うリスクを分散のための1候補ですので、全く頼り切ってしまうのは危険です。
宅配型というように、宅配業者や道路状況の被害次第では全くあてにならない可能性があります。
2つ目に、預けた荷物の取り出しはインターネットで依頼するので、インターネットに接続されているスマホやPCなどの端末が必要になります。
電波が受信できない、機器のバッテリーが切れて充電できない、といった環境では当てになりません。
3つ目に、なんでも預けられるわけではないので、何を入れるかじっくり検討する必要があります。
「発生から数日から数カ月で必要になり、箱に入れて預けられるもの」という基準で、ガイドラインに沿ってアイテムを選びましょう。
どんな宅配型トランクルームが使えそう?
宅配型トランクルームは今日本で人気急上昇のサービスで、選ぶのが難しいほど数多くあります。
ここでは、筆者がおススメする宅配型トランクルームをご紹介します。
防災ゆうストレージ

日本郵便株式会社の、災害時に特化した宅配型トランクルーム「防災ゆうストレージ」があります。
事前に災害時に必要とするものを預けておき、災害発生後など必要になったら取り出しを依頼して、自宅や避難先など届けてほしい住所を指定し届けてもらうというものです。
基本的には一般的な宅配型トランクルームと同じ感覚で使用することができますが、災害時に特化した特徴として、専用ボックスがポリプロピレン製の収納ボックスという点です。
段ボールとは違い、取り出した後も腰掛けとしてなど実用的なツールとして使い続けられるので、避難所など自宅以外の場所への避難時などは特に役立ちます。
また、一度取り出した後も同じボックスを利用して再度預けるこができるので、無駄なく定期的に中身を入れ替えすることも可能です。
預けるものの一例として、備蓄用の食品や生活用品といった災害後に費用な物資、災害で失いたくない大切なアルバムや思い出のアイテムなども可能です。
保管先は、宅配型トランクルームの代表格ともいえる倉庫業の大手「寺田倉庫」が管理する倉庫なので、安心して預けることができます。
さらに、「防災ゆうストレージ」の特徴は郵便ならではの小回りが利く配達システムのおかげで比較的届きやすい環境が整っているという点です。
全国に受取場所がたくさんあるので、もし指定した住所まで届くのが難しいとしても、取りに行きやすい環境が整っています。
宅配型トランクルーム最大手の寺田倉庫が日本郵便と共同企画した宅配型トランクルーム。
災害時の利用をメインとしている唯一のサービス。取り出しの際は場所や受取人を自由に指定でき、取り出し後も再利用可能。
| 運営会社 | 寺田倉庫株式会社 日本郵便株式会社 |
|---|---|
| 提供開始 | 2022年2月 |
| 保管 | 自社 |
| 登録方法 | ウェブサイト |
| アプリ | なし |
| 最短集荷日 | 当日 |
| 最短配達日 | 3営業日 |
| 祝日、連休対応 | 一部対応 |
| ダンボール提供 | 有料提供(自前は使用不可) |
| 早期取り出し料金 | なし |
| アイテム撮影 | なし |
| 空調 | 要確認 |
| 支払方法 | クレジットカード |
| 対応エリア |
|---|
| 全国 |
minikura(ミニクラ)

「高価な専用ボックスではなく段ボールで十分」という方なら、同じく寺田倉庫株式会社が提供する「ミニクラ」がおススメです。
ミニクラは、防災とは関係なく一般的な宅配型トランクルームとなります。
無料の専用ボックスまたは自前で用意した段ボールで預けることができるので、「防災ゆうストレージ」よりも箱にかかる費用を抑えて預けることができます。
また、無料の専用ボックスは4種類用意されているので、自分が預けたい荷物の量に合わせて箱の大きさを選ぶことができます。
預けられるものは「防災ゆうストレージ」と同じく、防災用の備蓄品や失いたくない思い出のアイテムを入れておくことができます。
配送はヤマト運輸(一部地域は「PickGo宅配」)ですので、日本郵便と再開のスピードに差ができる可能性はありますが、2024年の能登半島地震の際は、配送遅れの解消を共同で取り組むこともあり、大きな差はないでしょう。
「ミニクラ」の特徴は、預けた荷物の中から必要なアイテムだけ取り出すことができる点です。
例えば、1つの箱の中身に思い出の品と備蓄品が混ざっている場合、思い出の品はそのまま預けておいて備蓄品だけ取り出すということができます。
ただし、一部のアイテムを取り出した箱に再度アイテムを入れることはできないので、可能ならできるだけ1箱にたくさんの備蓄品を入れるようにし、すぐに必要ではない荷物は別の箱で預けた方が良いでしょう。
| 運営会社 | 寺田倉庫株式会社 |
|---|---|
| 提供開始 | 2012年9月 |
| 保管 | 自社 |
| 登録方法 | ウェブサイト |
| アプリ | なし |
| 最短集荷日 | 当日 |
| 最短配達日 | 当日 |
| 祝日、連休対応 | 対応 |
| ボックス提供 | 無料 (自前は使用不可) |
| 早期取り出し料金 | あり (入庫から2ヶ月間) |
| アイテム撮影 | あり |
| 空調 | あり |
| 支払方法 | クレジットカード |
| 対応エリア |
|---|
| 全国 |
\読書応援キャンペーン実施中!/
2つのサービス内容を比較
| サービス名 |  防災ゆうストレージ |
 ミニクラ HAKOプラン |
 ミニクラ MONOプラン |
|---|---|---|---|
| 宅配業者 | 日本郵便 (ゆうパック扱い) |
ヤマト運輸 (一部PickGo宅配) |
ヤマト運輸 (一部PickGo宅配) |
| ボックス素材 | ポリプロピレン製 (カバーは段ボール) |
段ボール | 段ボール |
| 最小ボックス | 専用ボックス〈小〉 | レギュラーBOX | レギュラーBOX |
| 箱サイズ(外寸) 幅×奥行×高さ(cm) |
40×39×37 (3辺合計 116) |
38×38×38 (3辺合計 114) |
38×38×38 (3辺合計 114) |
| 月額料金 | 275円 | 320円 (13ヶ月目から300円) |
380円 (13ヶ月目から360円) |
| 重量上限 | 13.5kg | 20kg | 20kg |
| 撮影 | 不可 | 不可 | 30点まで |
| アイテム取り出し | 不可 | 不可 | 可 |
まとめ
災害用の備蓄についてトランクルームのプロの目線でご紹介してきました。
トランクルームを活用して備蓄品を収納すると、次のようなメリットがあります。
- トランクルームを活用すると、家の貴重な収納スペースを備蓄品で埋める必要がなくなる。
- トランクルームに備蓄品を収納するとリスク分散になる。
- トランクルームを借りておくと、災害時にセカンドスペースとしていろいろな用途に使えるのでとても便利。
近くに希望のトランクルームが見つからない時は、全国どこでも利用できる宅配型トランクルームという選択肢もあります。
ただし、一般的なトランクルームでも宅配型トランクルームでも、災害という非常事態では確実に頼れるものではないことを理解し、あくまでリスク分散の手段の一つとして考えておくようにしましょう。
様々な有事がいつでもどこでも降りかかる可能性がある時代ですので、早めによく準備して備えるなら、自分や家族を守ることにつながります。












